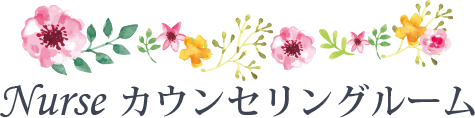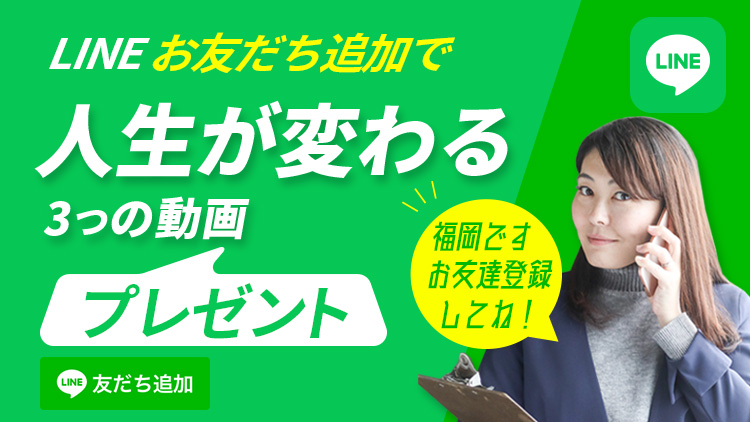不安がもたらす影響
2022-03-16
不安による影響
お友達登録で3つの動画・無料カウンセリングチケットプレゼント
↓ ↓ ↓
悩み事があったり、短期でストレスがかかるような状況にあると、それが原因となり、数時間あるいは数日間続く不安に襲われます。
飲み込めない
この時点で、身体に深刻な影響を与えることは多くありませんが、不安が何度も訪れ、それをコントロールできないと、その心の状況が身体に表れ始めます飲食する時、うまく飲み込めないのもよくある症状です。この症状は嚥下障害と呼ばれ、不安からくる症状です。これは唾液の分泌腺が関係しています。
逃げたいという思いがどこかにあると、不安が生じます。不安が生じると、体はまず、筋肉をサポートするために液体を体内に貯留しようとします。筋肉は逃げるために役立つからです。
不安により口の中が渇くのはそのためで、食べ物を噛んだり飲み込んだりするのが難しくなります。
頭痛
不安が静脈や動脈を収縮させてしまうのには、理由があります。それは、筋肉に、より多くの血液を与えるためです。
静脈や動脈が収縮すると、血液循環はよくなり、さらに血管の収縮を促進します。これが典型的な頭痛を引き起こす原因です。この種の頭痛は、朝の数時間あるいは午後に起こりやすくなります。
あごの痛み
不安やストレスにより、影響を受けやすい体の部位があります。それは、首、肩、背中、あごです。
特に朝、あごの痛みを感じたり、その痛みが耳の方まであれば、ストレスによる歯ぎしりをしている可能性があります。ストレスや不安により、寝ている間、歯を噛みしめているのです。
この症状がある場合、病院へ行きましょう。歯ぎしりの改善には、マウスピースが有効ですが、そもそもの原因である不安を適切にコントロールし取り除くことも重要です。
普段よりもお手洗いに行く回数が増える
これは経験がある人もいるでしょう。 テストや就職面接など不安が大きくなる状況で起こるものです。
実際、不安を感じている時、腎臓が作り出す尿の量は減るのです。それは、先ほどご説明した通り、体が体内に液体を蓄積しようとするためです。また、より素早く逃げられるよう不要な体重を減らすため、脳がお手洗いに行くように指示します。「たった数滴」しか尿が出ないほど何度もお手洗いに行かせ、尿を減らそうとするのです。
ひどい不安は肺に影響を与えます。呼吸のペースが速くなり、酸素が溜まりすぎると、次の二つのことが起こります:一つ目は過呼吸、そして二つ目がこの非現実感です。
脳が状況を適切に処理できなくなり、この感覚をもたらします。
ぜんそく、アトピー性皮膚炎といったアレルギーの病気も、ストレスによって起こりやすくなったり、悪化したりすることがあります。
強い緊張状態によってお腹を下した経験がある方も多いかと思います。ストレスによって胃や腸の動きに異常をきたし、胃の痛み、下痢・便秘、逆流性食道炎などを引き起こすケースが見られます。
腰痛
ストレスが原因で腰痛が起こることもわかってきています。ぎっくり腰や椎間板ヘルニアといったような整形外科の問題によって起こる腰痛のケースもありますが、そういった問題が見られないにもかかわらずちょっとした痛みがずっと続くような場合、ストレスが原因の慢性腰痛が疑われます。
うつ病や不安症(不安障害)といった心の病気にも、さまざまなストレスが関係しています。大きなストレスがかかることで脳の機能に何らかの失調が起こり、心や体に症状が現れます。
社会生活を送るうえでストレスは避けられません。たまり過ぎていないかときどき点検し、早めに対処するようにしましょう。
お友達登録で3つの動画・無料カウンセリングチケットプレゼント
↓ ↓ ↓