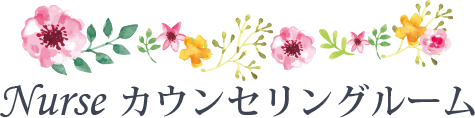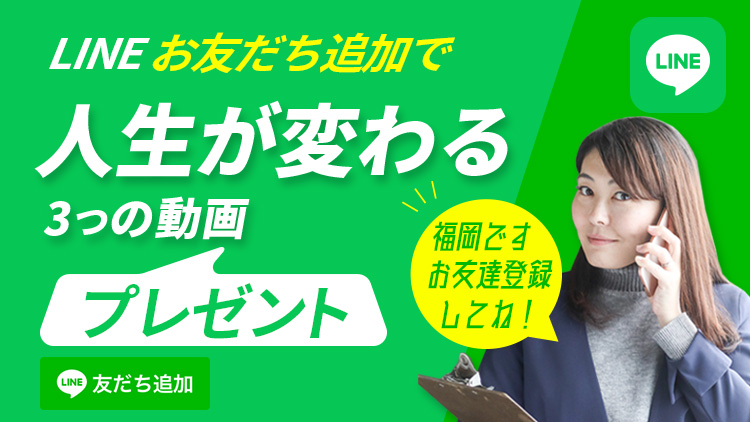パワーハラスメント
2021-03-02
あなたのストレスの中には解決できないハラスメントがありませんか?
ハラスメントとは、いろいろありますが、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントドクターハラスメント(医療従事者の、患者や家族に対する治療や生活の強要)なども指摘されるようになってきましたね。現役で看護師をしていますので、なかったとは言い切れないところがあります・・
そもそもハラスメントとはどう意味か知っていますか?ハラスメント(Harassment)とはいろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。
「パワー・ハラスメント」とは?
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
職場のパワーハラスメントとは、(厚生労働省より)
「2020年に、職場におけるハラスメントの規制が強化され、内容も見直されています。」
そもそも、会社にはハラスメントをほっといてはいけないという法律があるんです!!
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
「職場」とは
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
(その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意か)といったことを考慮して個別に行う必要があります。
「労働者」とは
正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用する全ての労働者をいいます。
①~「優越的な関係を背景とした」言動とは
業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者に対して、抵抗や拒絶することができない関係を背景として行われるものを指します。
②~「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは
当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
- 例
・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者の関係性等)を総合的に考慮することが適当です。
その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度と、それに対する指導が重要な要素となること(適切な指導をされていたのか)についても考慮。
なお、労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、職場におけるパワーハラスメントに当たり得ます。
③~「就業環境が害される」とは
労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために、「能力の発揮に重大な悪影響が生じる」等の当該労働者が就業する上で支障が生じることを指します。
なお、言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。
具体的パワーハラスメント
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
どうしたらいいでしょう。
まず、身近で信頼できる人に相談する。そこで解決することが困難な場合には、相談窓口に申し出るなどの方法を考えること。社内や学校にない場合は、我慢しない。恥ずかしい事でもない。守秘義務がある相談先に相談。無料相談もたくさんあります。
一人で我慢したり、考えないようにしたり、受け流しているだけでは必ずしも状況は改善されないので、勇気をもって行動しましょう。
「そんなことできたら悩まないよ。」と思うかもしれません。でも実際何か行動に起こさないと何も変わりません。
このSNSの発達した現代。人の情報。(特に誹謗)はすぐに炎上し大きくなって広がってゆく傾向にあります。業務委託をしていず、内部で選ばれたスタッフが行っている場合。私はあまり信用しません。過去の体験からも。
ですから大きな企業のメンタルサポート、働き方改革部門はあまり信用しなくなり、悩んだときは、どこともつながりのない中立な位置で見守ってくれるところを私はまずお勧めします。
話が大きくなると相手への事実確認。両者からの話を聞いたり他の社員へのアンケートがあったりと、やはり個人は見つけられやすくなり、仕事も学校も行きづらくなってしまうことになると思います。
ですから、私のような個人のメンタルカウンセラーや、健康相談者、厚生省のような大きなところ。労働基準監督所でも構いません。話してみてから相談者を変えたっていいんです。時間と体を無駄にしないてください!
また、ハラスメントを受けた日時、内容等について出来るだけ詳しく記録しておく、また、可能であれば第三者の証言を得ておくことが望ましい。(信用のできる人。)録音しておくのも有効です。
例えば、会社に相談室がある場合、(信用がある場合ですが、)パワハラはまず訴えずに、「ちょっとご相談なんですが・・」「同僚から聞いたんですが・・・。」のように前置きを置いて反応を見るのも手です。
相手は自分よりも人生経験や仕事経験がある方が任務にあたっていると思います。はっきり言って、完全に信じるのは会社や、学校の職員(委託は別)と相談をし、1、どう変わっていったか、2,関係性を悪化させるような事態になっていないか、もしくは話したのに全く変わらず、3.逆に我慢しなさい。と激励されてしまった。など評価しましょう。
一度は「共感してくれる人がいてよかった」と落ち着くかもしれませんが、一時のみです。結局根本的なことは改善されないのです。ですから時間と様子を見ながら行動する必要があります。その間は、信用のある、全く別の友人や相談者に話をして気を紛らわしておく。もしくは民間のカウンセラーに話を聞いてもらいながら今後の対応について考えるのもよいと思います。
これらのハラスメントが起きると、被害者はもちろんのこと、職場全体の生産性が低下し残業が増える。余計に上司のあたりも強くなっていきますよね。また会社のイメージが低下し企業にも大きな損失を与えることになります。
このため、ハラスメントへの対応は、人事労務管理の重要課題の1つとなっていて、大企業はもちろん、中堅・中小企業でもハラスメントが発生したときの対応枠組みを整備するところが増えてきています。
どんな立場であってもやっていい事、悪い事があります。
自分が仕事ができなくたって、障害があったって、卑下に扱われる必要はないんです。
今の環境・人、システムに、なんかおかしいな?と感じたら、一度ご相談ください。
是非ともお力になります!