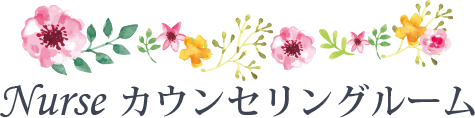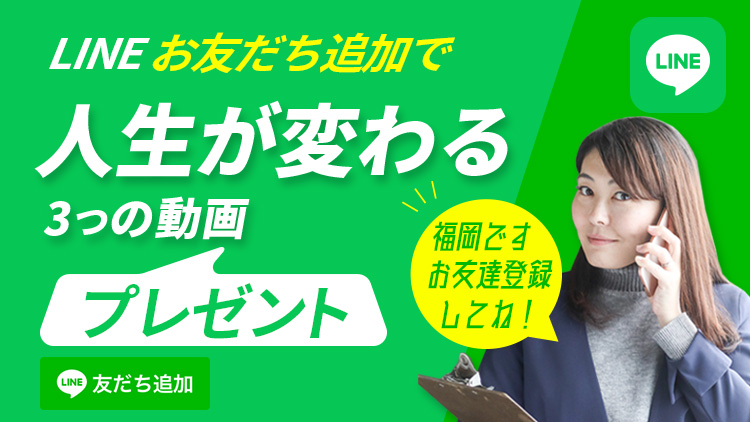コミュニケーションスキル
2021-02-14
看護師として、専門家として学んできたことをお伝えしたいと思いますので、何かのヒントになればと思います。
心理学者。ユング・フロイト・アドラーが有名です。
フロイトもアドラーもほぼ同じ時期のヨーロッパ・オーストリアの精科科医、心理学者です。
フロイトはすべての人の人格、行動は過去の環境や経験によって作られ、今がある。現在の人格形成、考え方には過去ががならずかならず影響している。なので紐解きが必要。と考えています。紐を解いて分析していくことは、過去にあった自分をマイナスにしているであろう事を振り返るため、精神的につらくなってしまうことが多いです。
やや後ろ向きです。
アドラーはストレスや悩みの原因のほとんどは人間関係。
と言っています。
このようなところから現代の人間によく知られるものとなります。
フロイトの考えは一部同じですが、違うのは、人は過去が原因となることに限定し、過去にコントロールされて行動するものではなく、
「過去はどうしようもないもの。と捉えること。
今後は目標に向かって行動するものです。」
と言っています。前向き思考。です。
私は現実的で前向き思考のアドラーの考え方が好きです、今日はアドラー流で考えていきたいと思います。
人間関係とは、①自分②相手③関係性④環境の4つが関連しています。この中で問題点として、改善しないと関係構築ができないとしたら、どこから手を付けますか??
4は相当な努力が必要になります。時には職場を・学校を変えることになります。
3の関係性とは、自分と相手の関係性です。上司なのか、親なのか、会社全体なのか。
2の友人なら距離を置く等でどうにかなっても、先輩や上司だった場合逆に関係性が悪くなるリスクがあります。
となると、人間関係を円滑に進めていきたいと願うならば、①自分を変える。ことが自分でできる一番手っ取り早い改善方法となります。
しかし、今までできなかったことを今から変えることも難しいことです。
簡単にはできないからストレスになってしまっているのですから。
自分を変えるということは、相手の考え、行動を察し、柔軟にとらえて自分がどう行動することができるか。が大切になってきます。
ですがそれにも準備が必要です。
まずは自分の傾向、思考を考え、ゆがみ(偏った考え方)がないかどうかを探してみましょう。
例として、コミュニケーションや人間関係の難しさ、ストレスを感じやすい人の傾向として③つ挙げて説明してゆきます。
- 相手の会話の仕方や、行動に敏感に反応し、イライラとすることがある。
② 「あの人がああ言った。こう言ったけど、おかしいよね?」「こうしてくれない。」と 人のせいにしがちな人。
③ 自分をダメ人間と思い込む。悩みを一人で抱え、うまく意見がいえず、相手に振り回されるタイプ。
を上げました。
①の相手の話す言葉や相手の行動に敏感に反応し、イライラしてしまう傾向にあたる人。は、一言で言うと真面目なんです。
だけど、相手の言葉、行動を自分基準にして考えていることが多いんです。
自分が基準で自分の物差しを常識と考えてしまうため、「ふつうは○○って考えない?」とか「ふつうはさ、○○って言うでしょ?」とか、「せっかくしてあげたのにさ。」、「ほんとは~すべきでしょう。」などと、~すべき。~のに。という言葉をよく使っていませんか??
これがイライラの原因になっています。
なぜならこれらは、自分を基本にした考え方なので、相手がそれと違う行動・言動をしたときに感覚にずれが生じてしまいストレスと感じてしまいます。
例えば善意でしたことが、意外に反応が悪かった時、がっかりしたり、いら立ちを感じたりしますよね。しかしながら、行った行為は自分の自己満足からしていることで、お願いされたわけではないんです。
ですが、その結果得られた反応が期待通りではなかったことで相手との感覚のズレが生じてしまいます。
人の思考、行動は自分の考え方が違って当然なことなんです
それは、それぞれの人が生まれた時代背景・環境、また人生経験が違います。
自分とは違って当然ですよね。
細かい家族構成、宗教なども関連するともっと違って当たり前なんです。
しかしこれに対してイライラと感じてしまう方は、自分が今まで生きてきた生育(生まれ、育った)環境、経験から得たことが常識で、正解であることと考えがちで、自己主張の強い方、自己中心的思考な方。自分の考えが常識。と思ってしまいがちな方が当てはまります。
これは②にも当てはまるものです。
相手の反応を自分だったらこうするのに。こう言うのに。という考え方にあてはめ、相手の反応を、自分の考えをもって決めつけてしまうこと。自分の感覚の枠以外の考え方はおかしいもの。自分の常識とは違うもの。と思ってしまうことで、相手との感覚のズレが生じます。
このズレがストレスとなり人間関係に不快感を感じることになります。
ではどうしたらよいのでしょうか。
簡単に言うと、相手が誰であったとしても、「相手は自分ではない。」ということを念頭に置いて接する。ということです。
脳を柔らかくし、どんな場合でも自分の考えは後にして、まず相手の思考、傾向を察する。傾聴するということからわかります。
相手を認められるように相手の立場で考える。枠を広げて考える。ことが必要です。
ですが、いきなりその場に立った時できるかと言ったら、絶対にできず、はじめはいつもの自分に戻ってしまいます。もしくは頭も中では言い返したくて仕方ない衝動あるはずです。
ですから日々の生活の中で、自分がどう感じているか、どう行動したかを振り返る練習をします。。
これを繰り返すことで、自分の癖やキーワードが出てきますので、それに気づいたらあとは直していくだけ。
どんどん対応できる自分になっていきます。日々努力です。
3の「自分をダメ人間で、自分から発信できずに流されてしまう。タイプ」の方は、
これは先ほど話したアドラーの心理に当てはまります。「流されているほうが楽でいい。」と感じる人はまずストレスにはなりません。
「ダメ人間と感じ、いつも流されてばっかり」だけれどこのままでいいのかな。このままでは嫌だ。」と不快に感じ、打破したいと考える向上心のある人が、打破できずにいる自分にストレスとなってしまい、コミュニケーションをとることを不得意と感じ、自分にダメ人間とレッテルを張ってしまってる場合もあります。
しかし
誰から見たダメ人間なのでしょうか?
誰と比べたダメ人間なんでしょうか?
今まではなしてきた内容と同じです。ダメ人間と判断しているのはあなた自身ではありませんか?
ストレスとなっているということは、「自分の意見が言えない。流されてばかりいることを打破させたいと思っているからだと判断できます。しかし中には自分を卑下しておくことで「私には優しくしてください。期待に応えられないかもしれません。と」防衛線を張って逃げていると思われることがありますので注意が必要です。
自分のことは自分で決めなければなりません。人に言われたから。では継続できずに諦めてしまいます。
自分で考えて決めたんですからやるしかないですし、修正もできます。
すべての自己決定権は自分だけのものですから、
自分を変化さる努力をしなければいつまでたっても今の立場からストレスを感じない自分へは変化してはいきません。
以上のようにコミュニケーションは自己を知ること。から始まり、必要時は修正する。この繰り返しによってスキルアップできます。その修正には練習が必要です。
そして、自分が何に向かっているのかを知り、それに向かうには何をしないといけないのか。
を考えることでより円滑で柔軟な人間関係が構築できるということです。