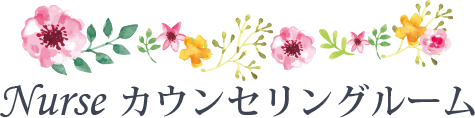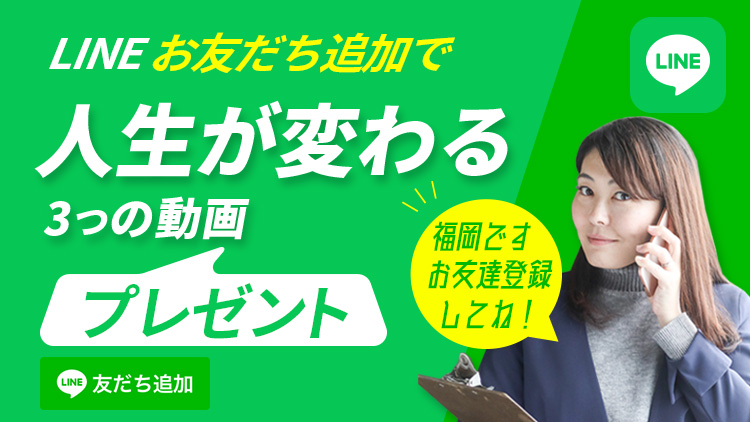子供・大人の引きこもり問題 (不登校)
2021-03-08
引きこもり
今回はコロナが原因で引きこもってしまった事例が増えている引きこもりを、いろいろな年齢層、原因から考えてみたいと思います。
「引きこもりってどんな状態のことを言うの?」
国の定義では、「仕事や学校などの社会参加を避け、家にこもる状態が半年以上続くこと」を引きこもりとしています。
その中で、精神的な疾患はないのにも関わらず、家に引きこもってしまう状態を「社会的引きこもり」と言い、現在では、引きこもりと言うと、社会的引きこもりを指すことも多くなっています。
引きこもりが長期化した場合、40代や50代の引きこもりの人を70代や80代の親が支えなくてはならず、問題が深刻化していきます。この現象は、「7040問題」「8050問題」と呼ばれています。
もし、我が子が引きこもっている状態で、家庭内が安定してしまっていると、「もっと本人が大きくなってから考えようかなぁ」など、考えることを先延ばしにしてしまうことがあります。
「なぜ我が子は引きこもってしまったんだろう?」
このように、「どうしてだろう」「どうしたら引きこもりから脱却できるのだろ」と考えこんでしまっているご家族の方も多いと思います。
引きこもりの原因探しをしたとしても、正しい答えにたどり着けるのかは、いろんな要因が重なり合ってのことなので難しいところです。
しかし、原因について知ることで解決できるケースもあります。
引きこもりになりやすい人の特徴として以下のことが考えられています。
- 完璧主義の傾向がある
- プライドが高い
- 理屈っぽく、執念深い
- いじめられたことがあるなど、過去に何らかのトラウマがある
- 人とコミュニケーションを取ることが苦手
- 引きこもる以前は真面目で、学校の成績も良かった
他にも、不登校が長引いて、その結果、そのまま引きこもり生活に陥ってしまうケースもありますタイミングを逃していけなくなってしまった場合等。
引きこもっている状態で、「引きこもり」だと判断するには、まずはその「引きこもり」状態が、何らかの心身の病気の症状である可能性があるのかないのかをきちんと吟味した上で、判断することが大事になります。
そこをスキップして、「引きこもり」状態にだけ焦点をあててしまうと、アプローチ法を間違えてしまう可能性があり、かえって何年も引きこもり症状を引き延ばしてしまうことにもなりかねません。
・親が原因であるとか、親が悪いというようなものではなく、親との関係形成がうまくいってないことが原因になります。外界へ関係を広げられるコミュニケーション能力に発展しません。逆に、双方に歩み寄りの姿勢があれば、「完璧」でなくても、外には出ていけるようになります。
・いじめが原因のケース
いじめが原因の引きこもりであっても、やはり重要なのは家族との関係になります。
外界が脅威となる時に、家族がどう動けるか、これまでの家族関係が試されているとも言えます。
些細ないじめやトラブルであっても、家族との絆が不安定であると、あっという間に大きな問題に発展してしまう可能性があるのです。
決して、家族がそうしたいじめ問題を解決することが重要なのではありません。
解決できない、仕方のない、不条理な気持ちを一緒に味わって抱えてくれる相手として、共に過ごしてくれるかが、子どもの安心感につながっていきます。
今後、また同じようなことがあっても、見捨てられない、立ち向かえるエネルギーをもらえる期待が持てるようになるのです。見直すべきは家族関係にあると考えてよいでしょう。
・病気が原因のケース
「引きこもり」が症状の病気には、
・広汎性発達障害
・強迫性障害を含む不安障害
・適応障害
・パーソナリティ障害
・統合失調症
などがあります。
医療機関で確認をした上で、対処を考えていく必要があります
子どものストレスに早く気づくことが大切です。一見すると、突然学校に行かなくなったと思われる場合でも、実は少し前からSOSのサインを出していることがほとんどです。例えば、次のようなことが見られたら、何らかのストレスを抱えている可能性があります。
【体調面】
朝、起きられなくなった。
頭痛、腹痛を度々訴えるようになった。
微熱が続いている。
【行動面】
学校や友達の話をしなくなった。
ボーっとしていることが増えた。
怒りっぽくなった。
情緒不安定になった。
これらの様子が見られたら、本人の話をじっくり聞いてみましょう。人に話を聞いてもらい、「つらかったね」「大変だったね」「頑張ってるね」などと認めてもらえると、少しストレスが解消されます。
「もし、学校を休みたいと言われたら?」
どんなに対策を行っても、お休みすることになる場合もあるでしょう。その場合は、それだけ原因となるストレスが大きすぎて、これ以上頑張るエネルギーが持てない状態にあるということ。
まずは、エネルギー切れの状態を回復させることが大切です。特に疲れ切っている状態の時は、本人が何かに取り組める状態になるまでは、なるべく学校を休ませましょう。
登校する場合は、保健室登校、短時間の授業参加にするなど、ストレスがかかりにくく、安心できる環境に置いてあげると、良いでしょう。学校との情報共有が必要です。
引きこもりが長引くと、家族と本人の間には共依存の関係が生まれやすく、そこからなかなか抜け出せなくなることがあります。
この共依存関係が持続しているうちは、外界とのつながり、社会生活への復帰を促すことはとても難しくなります。
いよいよ家族が年を取り、いつまで本人を養えるか不安になってきて初めて、社会復帰を考えるということが起こります。(7040問題)(8050問題)
このような状態になってしまったら、期限があるわけではないので、特に目標もないまま、共依存関係をずるずる続ける結果になりがちです。
お互いの気持ちを勝手に理解し、行動しあっている状態が続いていますので、まずは「相手がこう思っているだろうから、こうした」という心の中の動きを言葉にしていくことを心がけてみましょう。
必ずしも自分が考えている通りに相手が考えているわけではないことが理解してきます。
家族との関係でそうした確認作業が可能になったら、アルバイト先や外部施設で関わる人とのやりとりも、同じように言葉にして考えてみるとよいでしょう。
そうした目標づくりにも家族が一緒に取り組んだり、自分がどんな目標をもって仕事をしてきたかを話し合ってみたりしてみるのもいいでしょう。
家族の中で金銭的なルールを話し合って作り、それを守っていくことで、まずは適切な金銭感覚を育てることが必要になります。
経済的な自立とは、単なる人間関係の形成だけではなく、生活する分の収入を得るために、多少の我慢や努力を強いられることも考慮する必要があります。
事前にそうした気持ちの話を家族間で必要があります。
厚生省からも引きこもりの子供から大人までの支援を打ち出しています。なかなかそこまで行けないのが実際のところだと思いますが、いつまでもそうしてはいられないということも念頭におき、大切な家族のため、残された時の自分のためにできること探ししませんか?